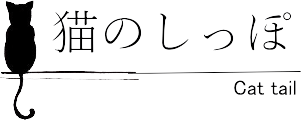猫は視覚以外の感覚も優れているため、失明しても日常生活に大きな支障を感じさせないことがあります。
そのため、飼い主が異変に気づくのが遅れてしまうことも少なくありません。
しかし、失明の原因によっては早期発見・治療で回復の可能性もあります。愛猫の異変に早く気づいてあげることが大切です。
猫が失明する原因と対策|快適に暮らすために飼い主ができること

猫は視覚以外の感覚も優れているため、失明しても日常生活に大きな支障を感じさせないことがあります。
そのため、飼い主が異変に気づくのが遅れてしまうことも少なくありません。
しかし、失明の原因によっては早期発見・治療で回復の可能性もあります。愛猫の異変に早く気づいてあげることが大切です。
失明の主な原因とは?
猫の失明にはさまざまな原因があります。
- 先天性の異常:生まれつき目に異常がある場合もあります。
- 加齢による病気:白内障や緑内障など、シニア猫に多い眼病。
- 外傷:高所からの落下やケンカ、事故による外傷。
- 感染症:猫ヘルペスウイルス、猫カリシウイルス、トキソプラズマなどの感染症。
- 高血圧:急激な網膜剥離を起こし、突然視力を失うことがあります。
飼い主が気づくためのチェックリスト
失明に早く気づくためには、次のような行動の変化に注目してみましょう。
- 物によくぶつかるようになった
- 暗い場所や段差を避けるようになった
- 視線が合わず、焦点が定まらない
- 目を細めたり、まぶしそうにする
- 目やにや涙が増えた
これらの症状に気づいたら、早めに動物病院で診察を受けてください。
失明しても快適に暮らすための環境づくり
視力を失っても、猫は記憶力や嗅覚・聴覚を使って生活できます。
- 家具や通路の配置を変えない
- 障害物を床に置かないようにする
- 段差や階段にはスロープを設置する
- 窓辺など、日向ぼっこのスペースを確保する
- 音や匂いで猫が安心できる環境を作る
壁にぶつかってしまう場合は、クッションなどで保護してあげるとよいでしょう。
食事・トイレの配置はそのままに
失明した猫は嗅覚に頼って食事やトイレの場所を認識します。
- 食器やトイレの場所は変更しない
- 猫砂やフードの種類も急に変えない
- 縁が低くて使いやすい器を選ぶ
- お水は毎日新鮮なものに交換する
フードはドライでもウェットでも構いません。健康状態や好みに応じて選びましょう。病気がある場合は動物病院に相談してください。
猫の感覚を活かす暮らし方
視力を失った猫は、聴覚や嗅覚がさらに鋭くなります。
- 鈴のついたおもちゃや音の出る合図で呼ぶ
- 飼い主の匂いがついたものを近くに置いて安心させる
- 大きな音や急な動きは控える
いつもと変わらぬ声やにおいが、猫にとって安心感を与えます。
早期発見・予防のためにできること
- 年に1回以上の健康診断を受ける
- 高血圧や腎臓病などの基礎疾患を定期的にチェック
- 目の健康も日常的に観察する
目に異常を感じたら、自己判断せずに獣医師に相談しましょう。失明の原因がわかれば、治療や予防策を講じることができます。
猫が失明すると余命に影響はあるの?

「失明=寿命が縮まる」と心配になる方も多いと思いますが、実際には、視力を失ったこと自体が寿命に直結するわけではありません。
猫は聴覚・嗅覚・触覚など、視覚以外の感覚が非常に発達しているため、失明しても日常生活に大きな支障を感じずに適応できます。
もちろん、見えないことによって猫がストレスを感じる場面もありますが、飼い主の慎重な配慮と適切な環境調整があれば、猫は安心して生活できます。その結果、元気に長生きすることも多いのです。
ただし、失明の背後に高血圧・腎臓病・糖尿病・甲状腺疾患などの基礎疾患がある場合、その障害が進行すれば体調に影響して寿命にも関わります。
したがって、「失明だけ」を捉えるのではなく、失明に至った原因疾患をしっかりケアすることが、愛猫の長生きを支えるカギとなります。
そのためにも、少なくとも年に1回の健康診断を推奨します。特にシニア期(7歳以上)になれば、半年ごとのチェックが理想的です。
片目だけ見えない?片目失明の原因と対処法

「片目だけ見えないかも?」と思う場面は非常に多くありますが、実は症状に気づくのが遅れるケースが少なくありません。
たとえば、猫がおもちゃにだけ反応しない、目をつむったままにしている—but 片目だけをかばっているように見える—というときは要注意です。
片目失明の原因には以下のようなものがあります。
注意
- 角膜のひっかき傷・潰瘍:ケンカや誤って家具にぶつかった衝撃など
- 慢性的な結膜炎:炎症が持続すると視力に影響が出る可能性がある
- 眼圧の異常(緑内障):片目だけ腫れている、目が出ている場合は急いで検査を
- 腫瘍や内出血:眼球やその周囲にできたものは視神経を圧迫する可能性があります
片目だけでも放置せずに診察を受けることが大切です。獣医師が診断するときは、スリットランプ検査・眼圧検査・場合によっては眼科専門病院でのCT検査が行われます。
治療方法は病因によりますが、点眼薬や抗生物質、降圧剤、手術が必要になる場合もあります。早期発見・早期治療が予後を左右するので、少しでも違和感を感じたらすぐ動物病院に行きましょう。
子猫が失明する原因とは?

生まれたばかりの子猫が目が見えないと気づくのは飼い主として非常につらいものです。
以下は、子猫の失明でよくある原因です。
- 先天性異常:視神経や網膜の発育不全、眼球奇形など
- ウイルス感染:ヘルペスウイルスやカリシウイルスによる「猫風邪」の重症化
- トキソプラズマ感染症:妊娠中の母猫から胎児に感染することがある
- ビタミンA欠乏:離乳が早すぎたり適切な母乳を飲んでいない場合に起こる
子猫は体力が未熟で免疫力も低いため、失明に至るまでの進行が早くなることがあります。そのため、子猫を迎えた直後からワクチン接種スケジュールを守ること、母猫の健康状態を確認して出産・授乳環境を整えることが非常に重要です。
もし目を開けない・目の腫れ・目やにの異常が見られる場合、不安なときは迷わず動物病院に連れていきましょう。治療が早ければ治るケースも少なくありません。
瞳孔が開いたまま?視覚障害のサインかも

猫の瞳孔(黒目の部分)が常に開いたまま、または明暗に関係なく大きさが変わらないときは、視覚機能に問題がある可能性があります。
本来、瞳孔は光の量を調節するために、明るいときは小さく、暗いときは大きく開きます。
しかし、光に反応しない場合や左右の瞳孔の大きさが異なる場合、以下のような問題が疑われます。
- 網膜剥離・網膜炎など、網膜にダメージがある
- 脳神経の障害や炎症
- 緑内障による眼圧の異常
- 瞳孔を開く薬が誤って目に入ったなどの外部要因
このような状態は早期治療が重要です。念のため、瞳孔のチェックは日常でも観察し、いつもと違うと感じたらすぐに病院へ相談しましょう。
失明した猫がよく鳴くのはなぜ?

失明によって視覚による情報が失われると、猫は不安や恐怖、孤立感を感じやすくなり、「鳴くことで安心を得よう」とすることがあります。
鳴く理由は主に以下のような場合です。
ポイント
- どこにいるのかわからず、自分の存在をアピール
- 暗くて不安なので「そばにいて?」と訴えるような行動
- 環境の変化(家具移動・家族構成の変更など)によるストレス
対応策としては以下がおすすめです。
ポイント
- 普段と同じ声・トーンで名前を呼ぶ
- 夜寝るときに飼い主の匂いがついた布などをそばに置く
- 音の鳴るおもちゃで方向を示す
- 夜間のライトや常夜灯で安心できる空間をつくる
鳴いているときに無視したり叱ったりすると、猫がより不安になる可能性があります。
目が見えない猫の気持ちを理解しよう

猫は言葉を話せませんから、「見える世界がない」「見えていた世界が突然なくなる」ことは、強い恐怖や混乱につながることがあります。
実際に、多くの飼い主さんからは「最初は壁にぶつかったり、隅っこに隠れたりしていたけれど、数週間で落ち着いて歩けるようになった」といった話を聞きます。
これは、猫が自身の感覚を再調整し、環境を「音・匂い・記憶」で把握するようになるからです。
猫の不安を軽減するために、次の対応が有効です。
- 生活リズムを崩さず、一貫した環境を保つ
- 新しい家具や寝場所は最小限にし、変化の際は少しずつ進める
- 壁や家具の角にクッションをつけてぶつかる衝撃を和らげる
- かけ声や音で猫の居場所を知らせる習慣をつける
「大丈夫だよ」「ここだよ」と優しく声をかけるだけで、猫の安心感はぐっと高まります。
🐾 総まとめ:失明しても猫は幸せに暮らせる

- 猫は視覚以外の感覚で生活でき、失明後も順応する力があります。
- 失明自体は寿命に大きく影響しませんが、原因疾患の管理が大切です。
- 片目失明や瞳孔の異常など、小さな変化にも注意を払いましょう。
- 鳴くのは不安や環境確認のサイン。優しく応えて安心感を与えましょう。
- 安定した環境と日常のケアが、猫のQOL(生活の質)を保ちます。
飼い主としてできることはたくさんあります。愛猫が見えない世界でも怖がらず、安心して暮らせるように、これからも気づきと対応を大切にしてください。
-

-
幸せな猫ライフのスタート!シニア猫との暮らしに必要な準備5つ
シニア猫との暮らしは、飼い主にとっても猫にとっても貴重なものです。しかし、年齢が上がっているため、若い猫とは違ったケアが必要です。 そこで今回は、シニア猫と共に幸せに過ごすために必要な準備の5つをご紹 ...
続きを見る